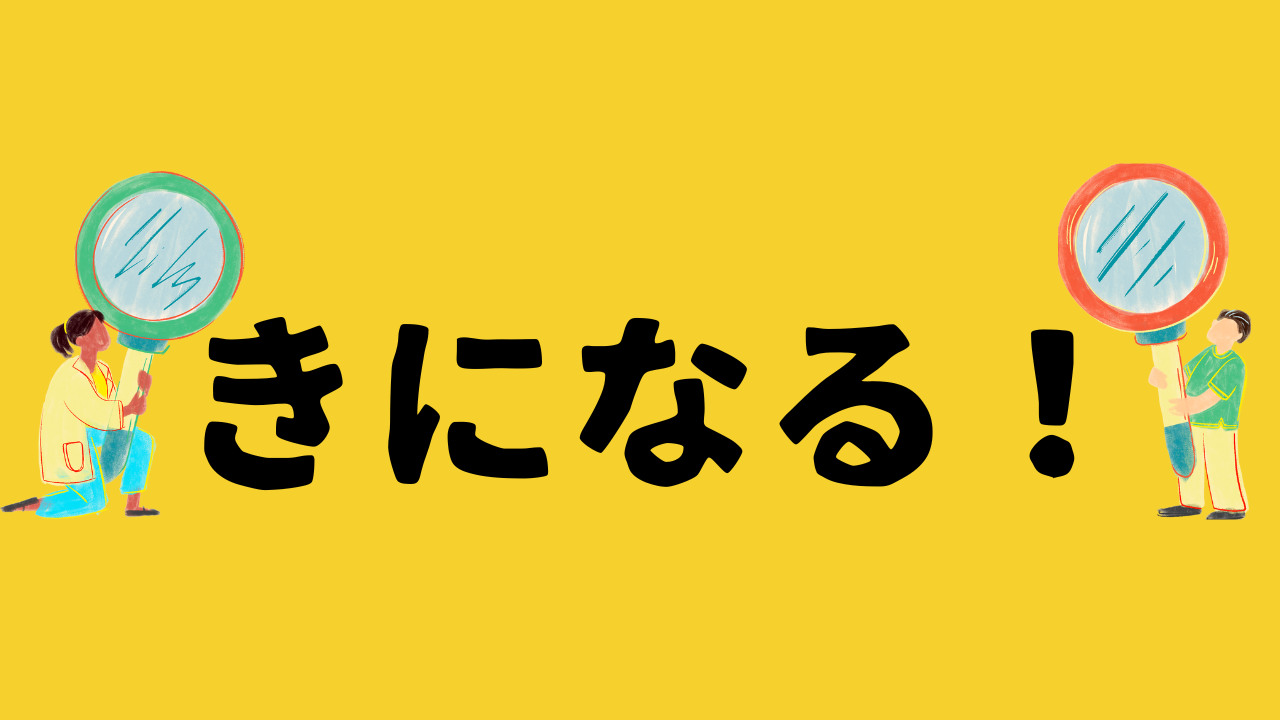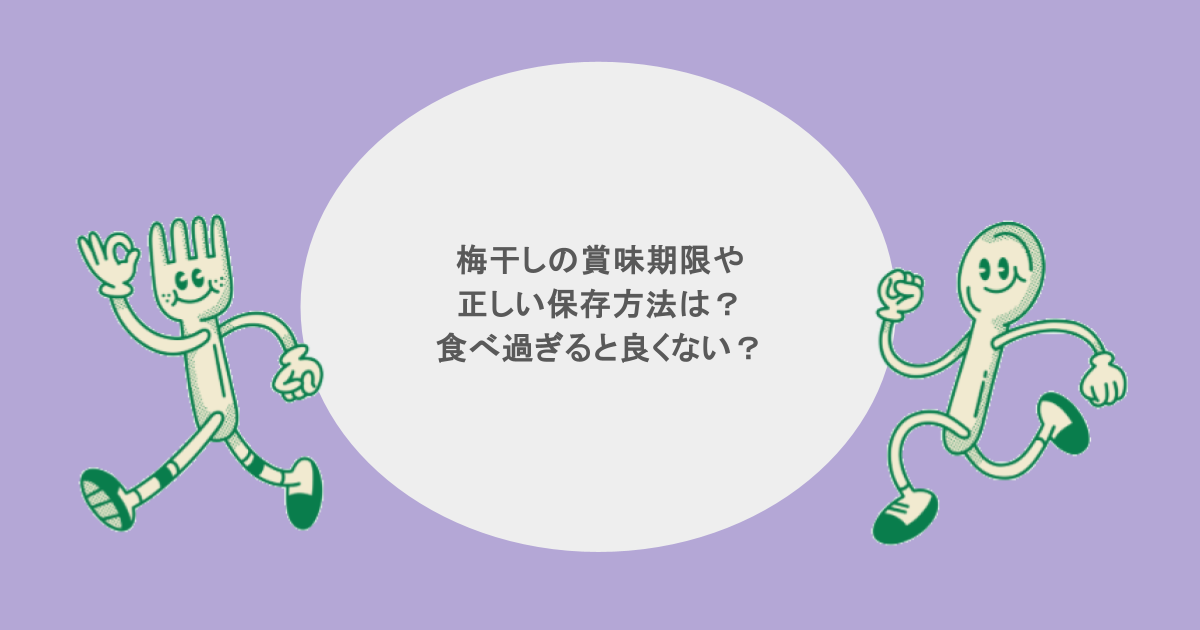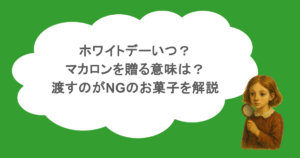梅干しは昔から保存食として親しまれてきた日本の伝統食品です。でも「賞味期限ってあるの?」「保存は常温でいいの?」と迷うことも。さらに、健康に良いイメージがある一方で、「食べ過ぎは体に良くないのでは?」と言われることもあります。
この記事では梅干しの賞味期限や正しい保存方法、食べるときに注意したいポイントをわかりやすくまとめました。
梅干しの賞味期限ってあるの?
市販品の梅干しには賞味期限があり、未開封であれば3ヶ月から6ヶ月程度が一般的です。そして、昔ながらの製法で作られた塩分濃度の高い梅干しには、賞味期限のないものもあります。きちんと保存すれば10年以上品質を保てる場合もあるのです。
市販品の未開封の梅干しは外気に触れていないため品質が安定しています。表示された賞味期限内であればおいしく食べられるでしょう。
一方で開封後は雑菌が入りやすくなり、痛みやすくなるため、保存方法に注意が必要。冷蔵庫で保存しなるべく早めに食べ切るのがおすすめです。
減塩梅干しは賞味期限が短い?
一般の梅干しが塩分濃度18%~20%なのに対して、減塩梅干しは塩分濃度が5%~10%程度と低めです。そのため保存性が劣り通常のものに比べると賞味期限が短くなります。
未開封のもので2週間から1ヶ月程度が一般的で、開封後は早めに食べ切ると安心です。塩分摂取を控えたい方に人気ですが、一般の梅干しにくらべて日持ちしないので、保存には十分注意しましょう。
手作り梅干しの賞味期限はどれくらい?
手作り梅干しは塩のみを使い、正しい方法で作られていれば市販品よりも長持ちします。明確な賞味期限はありませんが、保存状態が良ければ1年程度は日持ちするそうです。
天日干しや漬けこみ時間、保存容器の衛生状態によって日持ちする期間は大きく左右されます。長持ちさせたい場合は特に衛生的な環境と保存方法を意識してくださいね。
梅干しの保存方法
梅干しをおいしく、そして安全に楽しむためには正しい保存方法が欠かせません。保存状態が悪いと風味の低下だけでなく、カビの原因になることも。梅干しの種類や製法によって、適した保存方法は異なります。
また、保存容器の素材や形状、保存場所の温度や湿度などにも配慮が必要です。ちょっとした工夫でおいしく食べられる期間が延びるので、ポイントを押さえておきたいですね!
常温・冷蔵・冷凍のどれが正解?
塩分濃度の高い昔ながらの梅干しは、常温でも保存可能です。一方、減塩タイプや市販品の開封後の梅干しは冷蔵保存をおすすめします。長期保存したい場合は冷凍保存をしてください。
冷凍梅干しを解凍したものは日持ちがしないので、その日のうちに食べ切るようにすると良いでしょう。梅干しの種類や製法に応じて、保存方法を使い分けるのがポイントです。
保存容器はどんなものがいい?
梅干しの保存にはガラスや陶器の密封容器が最適です。酸に強く、におい移りがしにくいので風味を保つことができます。
ガラスの瓶で保存するときに気を付けてほしいのはフタの材質。鉄製のフタは塩分の高い梅干しと相性が悪く、錆びてしまうことがありますのでご注意ください。
密封容器での保存をおすすめする理由は、冷蔵庫内は水分が蒸発しやすく密封できていないと梅干しがパサパサに乾いてしまうからです。梅干しを取り出すときは清潔で乾いた箸を使いましょう。
梅干しは食べ過ぎると体に良くない?
梅干しは健康に良いイメージがありますが、食べすぎには注意が必要です。特に塩分が多く含まれているため、過剰に摂取すると高血圧やむくみの原因になることも。1日1~2個を目安に、適量を心がけることをおすすめします。
塩分の過剰摂取に注意
梅干し1個には約1~4gの塩分が含まれています。塩分が多く含まれているので、1日に何個も食べるとすぐに塩分過多になってしまうのです。ちなみに塩分の1日摂取目標量は、成人男性7.5g未満、成人女性6.5g未満と設定されています。
塩分のとりすぎは高血圧や腎臓への負担、動脈硬化のリスクを高める原因になります。特に高血圧の方や塩分制限が必要な方、小さなお子さんは梅干しの摂取量に注意が必要です。ほかの食事との塩分バランスも意識してくださいね。
食べ過ぎによる症状とは
梅干しを食べすぎると胃への負担が強くなり、胃痛や胃もたれを感じることがあります。また、腸内の塩分濃度が高くなることにより、下痢を引き起こすことも。
塩分には水分をため込む性質があるので、体内の余分な水分をうまく排出できなくなり、むくみやのどの渇きにつながることも考えられます。自分の体調にあった量を見極めることが大切です。適量をおいしく楽しみたいですね。
梅干しの栄養と健康効果
梅干しは古くから健康食品として親しまれてきました。その最大の理由はクエン酸やポリフェノールなどの栄養素を豊富に含んでいる点です。
1日1粒を継続的に食べることで体の調子を整える助けになることでしょう。毎日の食事にうまく取り入れ、健康維持に役立ててくださいね。
クエン酸で疲労回復
梅干しに多く含まれるクエン酸には体内のエネルギー代謝をサポートし、疲労物質の分解を助ける働きがあります。運動後は夏バテ気味のときに摂ることで、疲れを和らげる効果が期待できます。
また、クエン酸はミネラルの吸収を助ける作用もあり、栄養バランスのサポートにも。酸味が食欲を刺激してくれるため、食が細くなりがちな夏場にもおすすめです。
殺菌・整腸・免疫力アップにも期待
梅干しに含まれる成分には抗菌・殺菌作用があるといわれており、昔からお弁当に入れる習慣があるのもそのためです。さらに、クエン酸やポリフェノールには腸内環境を整える効果もあり、免疫力の維持にもつながります。
風邪予防や体調管理のサポートとして、日常的に摂るとよいでしょう。ただし、食べ過ぎには注意して体調に合わせた量を心がけてくださいね。
まとめ
この記事では梅干しの賞味期限や正しい保存方法、食べるときに注意したいポイントをわかりやすくまとめました。梅干しは昔ながらの保存食です。塩分の高いものは常温でも保存できますが、減塩タイプや開封後は冷蔵保存がおすすめ。保存容器や扱い方にも気をつけましょう。また、健康効果が期待できる一方で、食べ過ぎは塩分のとりすぎになってしまいます。1日1~2個を目安に、体調やライフスタイルに合わせて取り入れるのがポイントです。毎日の食事に梅干しを活用して、健やかにお過ごしくださいね!
あわせて読みたい:ラーメン二郎の頼み方&コールを総特集!これだけ知っておけば無問題