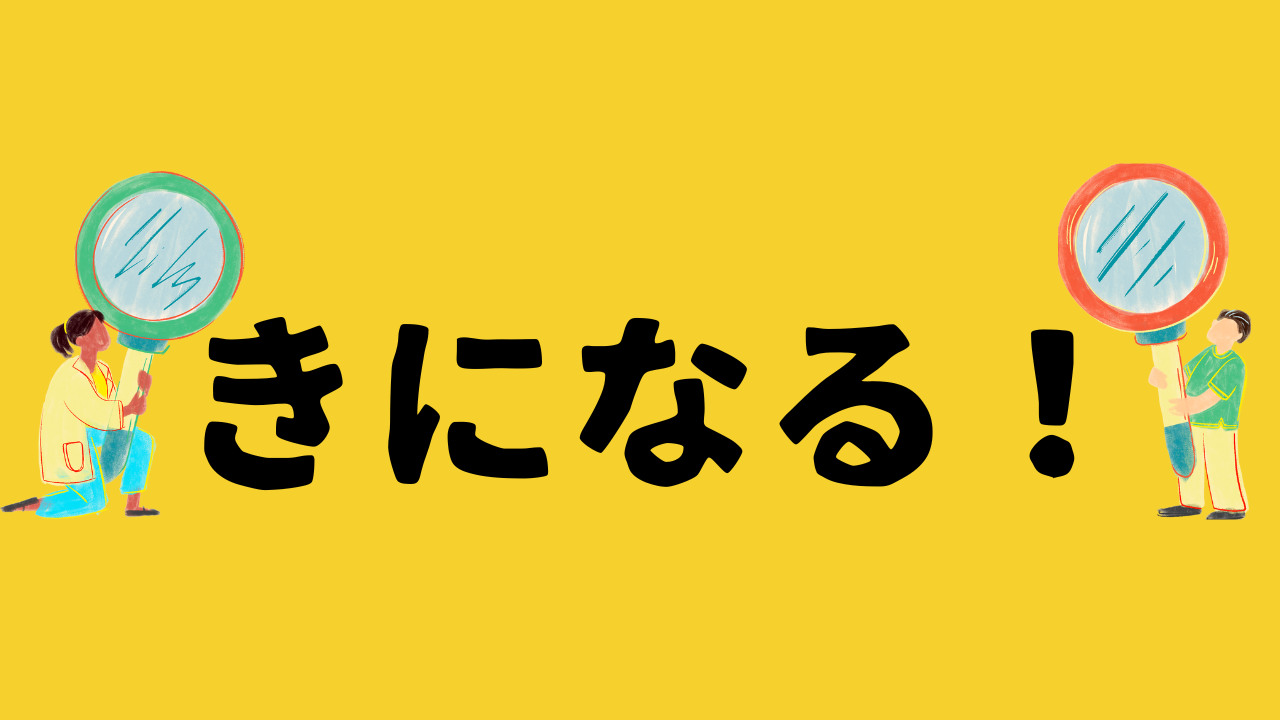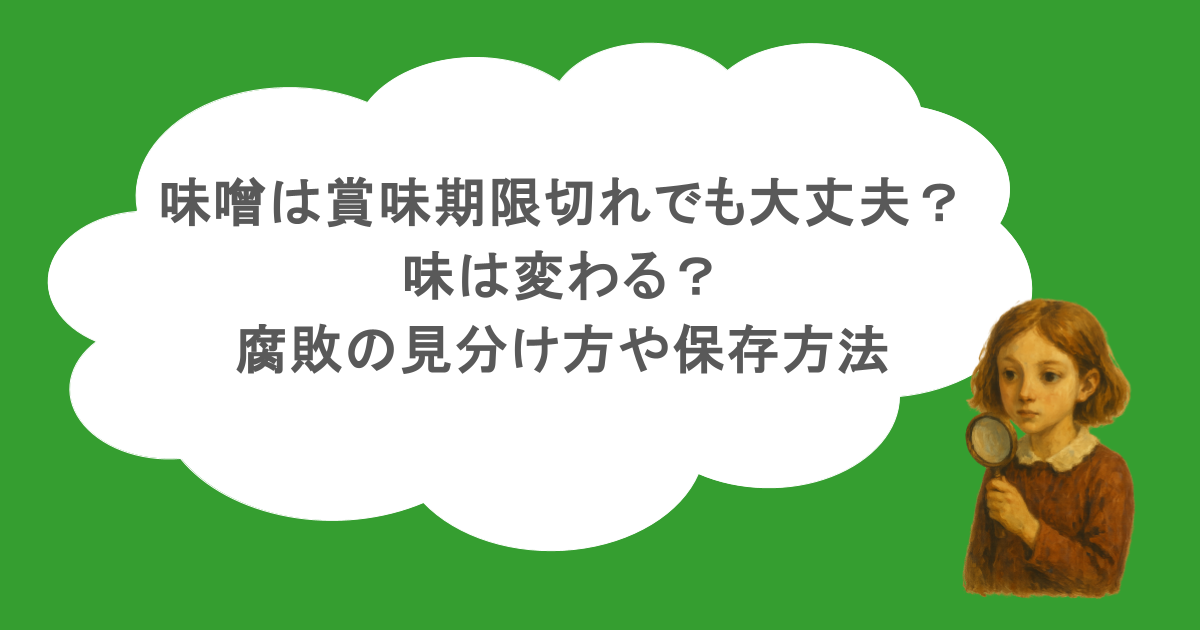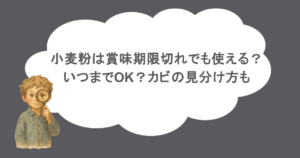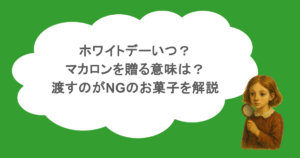日本食の料理をする上で必要不可欠な調味料として醤油と双璧となっているのが味噌です。味噌は醤油と同様に大豆の発酵食品の調味料であることから賞味期限などがわかりにくく、気づいたときには賞味期限切れとなってしまっている場合もあります。本記事では味噌の賞味期限切れに焦点を当て、味の違いや腐敗の見分け方、効果的な味噌の保存方法について概要を紹介していきます。
賞味期限切れでも大丈夫なのか?
味噌の多くのパッケージには賞味期限がパッケージに記載されていますが、これは未開封かつ涼しく乾いた場所という条件の場合には、期限超過後でも見た目・におい・味に異常がなければ使える可能性があります。発酵食品ゆえに熟成が進み、色や香りが変化することは珍しくないため、料理に使用した場合には元の味噌の味と異なってしまう懸念について十分留意が必要です。しかしながら、目に見えてカビが生えている場合や、強い異臭、糸を引いているたり、ぬめりがあるといった腐敗のサインがある場合には即廃棄が原則です。
期限切れ後いつまで大丈夫なのか?
未開封かつ常温推奨の涼所保管なら、味噌は数週間〜数か月の超過でも先述の腐敗に関係する異常なしなら使用可能な場合があります。なお開封後は冷蔵前提で1〜2か月を目安に早めの使い切りをすることが推奨されます。また減塩・白味噌・生味噌・だし入りはさらに短めに考えるのが無難です。加えて夏場や高温多湿の環境では味噌の劣化が加速するため、保存環境の状態には気を付ける必要があります。なおこれらの期限はあくまで目安であり、最終判断は「外観・におい・味」のセルフチェックで行い、迷ったら使わない判断をしましょう。
減塩タイプやだし入りの賞味期限が短い理由
減塩タイプの場合には、味噌ひ含まれている塩が少ないため、微生物の活動や酵素の反応が進みやすいと言われています。また酸化のスピードも速いことから味の劣化も速く、このタイプの味噌は早めに使い切らないと安全性も味も劣化してしまうリスクが高いです。また、だし入りの味噌の場合には味噌内に含まれる栄養が多いため、微生物にとって栄養過多となり反応が進むため賞味期限が短くなります。非加熱の生味噌という商品もありますが、こちらは加熱殺菌をしていないため、開封後も発酵が進むため味の変化が進みやすく、より注意が必要です。
味は変わるのか?
先述の発酵や酸化の進行により、味噌の味は時間経過とともに変質していきます。味噌の色は濃くなり、カラメル様になりまろやかになる場合もあります。この変化は腐敗の反応とは異なる自然な変化のため、すぐに使用不可となるわけではありません。しかしながら味噌から酸っぱいにおいや刺激臭、アルコール臭や焦げ臭さなど明らかに普通の味噌とは異なる味や臭いがした場合には使用中止を検討するをおすすめします。なお味噌の味見は米粒大で問題なく、少量にするようにしましょう。
味噌の袋の膨らみの判断
生味噌や未加熱の合わせ味噌では、酵母が生きていて発酵ガス(CO₂)で袋がふくらむことがあります。開封すると軽い“炭酸っぽさ”やアルコール香が抜け、通常の香りに戻れば多くは問題ありません。一方、強い酸臭・腐敗臭、内容物の分離や糸引き、著しい変色を伴う膨らみがある場合には賞味期限切れの危険サインです。開封して肩口に泡が絶えず湧く、粘つくなどの異常があれば廃棄しましょう。
腐敗の見分け方
賞味期限切れの味噌の腐敗は大きく分けて色と臭いと質感で判断することができます。緑や黒、毛羽立ちなどのサインが見えた場合にはカビが発生してい可能性があります。また腐敗臭やカビ臭、湿ったような臭いやアンモニア臭がした場合には腐敗が進行しているため使用はやめるようにしましょう。質感の変化としては糸を引いたり泡立ったりするような表面の変化が生じている場合も使用はNGです。なお腐敗による毒素は加熱によっても分解されないため火を通したとしても使用はできません。
腐敗ではない見た目の変化
味噌の表面に白い薄膜がはる「産膜酵母」は、酸素があると生えやすい酵母の一種で、カビとは別物なので使用できる可能性があります。アルコール含浸ペーパーや清潔なスプーンで厚めに取り除けば、残りは使用できる場合が多いです。また、白い粒状結晶はアミノ酸(チロシン)や塩の析出で無害です。なお先述のとおり、これらの変化以外の膜が綿毛状・色付き(緑・黒・ピンク等)・厚く盛り上がる場合はカビの可能性が高いので廃棄してください。
正しい保存方法
味噌は開封後は10℃以下を目安にした冷蔵が求められます。味噌の表面を平らにして空気層を減らし、味噌の表面にピッタリ密着するラップや落とし蓋をし、容器の天面にもラップ→フタの二重で酸素を遮断することで味噌を長持ちさせることができます。使用の際には清潔な乾いたスプーンを都度用意し、使ったヘラを容器へ戻さないことを徹底して味噌に雑菌が入らないように注意しましょう。また強いにおいの食品と同室保管を避け、におい移りを防ぐ必要があります。なお生味噌は特に低温管理を徹底し、減塩やだし入りは早めに使い切る前提で小容量を選ぶのが得策です。
種類の多い大豆食品
味噌以外にも大豆食品には豆腐やおから、醤油や豆乳などいろいろな種類がありますよね。大豆製品はプロテインも豊富で健康にも良く積極的に取り入れたい食品です。安いからと言って買いすぎてしまうと、気づいたら賞味期限が過ぎてしまっているなんてこともあるかもしれません。美味しく食べるためにも納豆 賞味期限切れなど注意が必要です。
まとめ
味噌をはじめとした発酵食品の管理は、見た目と臭いと普段の使い方に気を付けていれば意外と長持ちさせることができます。しかしながら味の劣化などの変化が発生するのは必然なので、できるだけ小分けにして早い段階で使い切ってしまうのに越したことはありません。また夏場などの高温多湿の環境の場合には特に劣化や腐敗のリスクが高いため、しっかりと冷蔵で管理する習慣をつけておく必要があるでしょう。